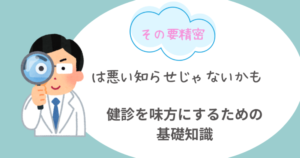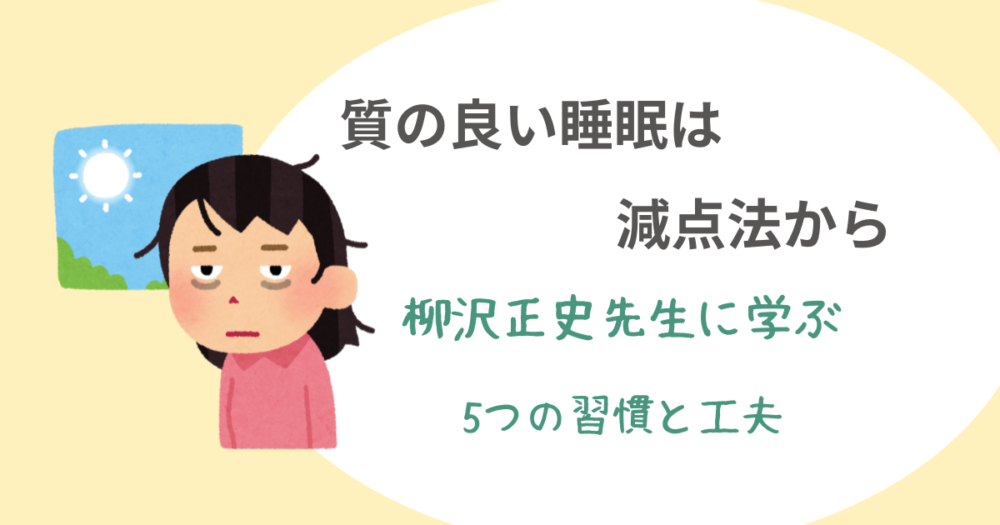毎日しっかり眠っているはずなのに、朝起きても疲れが残っていたり、なんとなく気分が晴れないことはありませんか?『年齢のせいかな・・』と思いがちですが、実は”眠りの質”が大きく関係しています。睡眠は単に体を休める時間ではなく、脳と体を修復し、心のバランスを整えるための大切なメンテナンスの時間です。最近では、睡眠不足が肥満や内臓脂肪の増加につながり、糖代謝やホルモンの働きにも影響を与えることがわかってきました。
柳沢先生をはじめ、睡眠研究の第一人者たちの研究からも『睡眠は健康の土台』であることが明らかになっています。私自身もその知見を取り入れ、日々の生活に少しずつ工夫を加えることで、体調や気分に変化を感じられるようになりました。この記事では、良い睡眠をとるための習慣と工夫をお伝えします。
睡眠の基本的な役割
私たちが眠るのは『疲れたから休むため』だけではありません。睡眠には、体と心の両方を支える大きな役割があります。まず、からだの役割としては、眠っている間に細胞が修復され、免疫力が整います。日中に受けたダメージを回復する時間が、まさに睡眠なのです。たとえば、肌の調子や体調の安定には十分な睡眠が欠かせません。
次に心の役割としては、脳の情報処理があります。私たちが日中に得た膨大な情報や体験は、眠っている間に脳内で仕分けされ、必要なものは記憶として残り、不要なものは捨てられます。これは脳内の『ゴミ出し』とも言われ、翌日の集中力や判断力に直結します。さらにホルモンの分泌も睡眠と深く関わっています。成長ホルモンや食欲をコントロールするホルモンは、主に眠っている間に働きます。そのため、質の悪い睡眠は肥満や生活習慣病のリスクにもつながるのです。つまり、睡眠とは単なる休息ではなく、『からだの修復』『脳の整理』『ホルモンの調整』という3つの柱で、私たちの健康を根本から支えているものだと言えるでしょう。
ノンレム睡眠とレム睡眠
| 特徴 | ノンレム睡眠 | レム睡眠 |
| 脳の状態 | 休息している | 活発に活動している |
| からだの状態 | 筋肉の緊張が保たれている | からだの力が抜けている |
| 眼球の動き | 動きがほとんどない | 素早く動いている |
| 主な役割 | 脳と体を休ませ、疲労を回復させる | 記憶の整理や定着、感情の処理を行う |
| 夢の見方 | ほとんど見ないか、内容のない夢を見る | 鮮明で物語性のある夢を見やすい |
| 割合 | 全睡眠時間の約80% | 全睡眠時間の約20% |
睡眠はスマホに例えるとわかりやすいかもしれません。
ノンレム睡眠=体力の充電(スマホのバッテリーをしっかり補充する時間)
レム睡眠=脳のアップデート(ソフトを最新の状態に更新する時間)
つまり、眠らないと『体は電池切れ』、『脳は古いまま』。これでは次の日のパフォーマンスは落ちてしまいます。
レム睡眠は『体は休んでいるけど、脳は起きている』状態。この時夢を見て体が勝手に動かないように、脳は強制的に筋肉を休ませ、体を動かせない状態にしています。金縛りは、このレム睡眠から覚醒する『切り替えの不具合』で、脳が先に起きて意識があるのに、体はまだレム睡眠モードで動けない状態です。
柳沢正史先生が教える『良い睡眠のための習慣』5つ
1.睡眠時間を確保する

先生は、何よりも睡眠時間を確保することが大事と言われています。日本人は先進国の中でも、睡眠時間が少ないとのこと。成人は個人差がありますが、6〜8時間必要と言われています。睡眠不足は『一晩だけならなんとかなる』と思いがちですが、実はお金の借金と同じで”負債”として体にたまっていきます。たとえば、毎日1時間ずつ睡眠を削っていると、1週間で7時間分の借金が発生。これを週末に”寝だめ”しても、返せるのは利子の一部だけで、元金までは戻りません。つまり、慢性的な寝不足は『ずっと返せない借金を抱えている状態』。気づかないうちに体や脳のパフォーマンスを下げ、生活習慣病や心の不調にもつながります。大切なのは『まとめて返そう』ではなく、日々しっかり睡眠時間を確保して”借金を作らない生活”を心がけることです。
2.寝室環境を整える

『夜のリビングが昼間になっていませんか?』夜なのに昼間のような強い光を浴びると、脳は『まだ昼だ』と勘違い。メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌が抑えられて、寝つきが悪くなります。スマホのブルーライトがよく悪者にされますが、実はリビングやダイニングの照明が強すぎることが問題。夜は間接照明や電球色に変えるだけで、睡眠の質がグッと上がります。人間は進化の歴史の中で、夜は暗い環境で眠るようにできています。現代のリビングの蛍光灯やLEDは、体にとっては『異常な光環境』。高級ホテルのような薄暗い環境や月明かりのようなやわらかい光を目安にしましょう。日暮れ時以降は、強い光を目に入れない努力をしましょう。
もう一つは『エアコンは体に悪い』『電気代がもったいない』と言って、寝る前にタイマーをかけていませんか?実はその習慣こそが睡眠の質を下げる大きな原因です。夜中に暑さや寒さで目が覚めると、深い眠りが分断され脳も体も休まりません。エアコンは朝までつけっぱなしでOK。むしろそれが”質の良い眠り”と”気持ちの良い目覚め”につながります。『暗く』て『静か』で『適温』の寝室環境を整えましょう。
3.眠りの敵は午後のカフェインと夜遅くのお酒

私たちの眠りを静かに妨げているのが、午後以降のカフェインと夜遅くのアルコールです。コーヒーや紅茶に含まれるカフェインは、脳を覚醒させる作用があり、接種してから5〜7時間は効果が続くと言われています。そのため、午後3時以降のカフェインは夜の入眠を妨げ、眠りを浅くしてしまうことがあります。デカフェやハーブティーに切り替えるのがおすすめです。
一方でアルコールは、一見『寝つきをよくする』ように思えますが、実は眠りを浅くし途中で目が覚めやすくするため、結果的に睡眠の質を大きく下げてしまいます。特に夜遅い時間のお酒は要注意です。楽しむなら寝る3時間前を目安に。『午後のカフェイン』と『遅い時間のお酒』を控えるだけで、翌朝の目覚めがぐっと変わります。
4.就寝前のお風呂で深部体温を調整

眠りに入るためのは『深部体温(からだの内側の温度)』が下がることがポイントです。お風呂で一度体をしっかり温めると、その後に体温が徐々に下がっていくことで、自然な眠気が訪れます。おすすめは就寝の90分前に40度前後のお湯に15分程度つかること。シャワーだけで済ませるよりもリラックス効果が高く、副交感神経が優位になり、寝つきやすさにつながります。
5.眠くなってから布団に入る+入眠儀式を持つ

『眠れないのに布団に入っている』のは逆効果。脳が『布団=眠れない場所』と学習してしまうからです。大切なのは”眠気を感じてから布団に入る”こと。眠れない時は無理に横にならず、静かに読書したり、ストレッチしたりして再び眠気を待ちましょう。また、毎晩同じ行動を繰り返す『入眠儀式』も効果的です。たとえば、アロマを焚く・お気に入りの音楽を聴く・日記を書くなど。脳が『この行動の後は眠る時間』と認識し、スムーズな入眠につながります。
睡眠と健康のつながり
睡眠は『休む時間』以上の意味を持っています。臨床検査技師として働く中で、睡眠の乱れが体のあらゆる機能に影響を及ぼしていることを強く感じることも。たとえば、十分に眠れていない人は血圧が上がりやすく、糖代謝やホルモンバランスも乱れがちです。実際に、睡眠不足は高血圧・糖尿病・心筋梗塞などのリスクを高めることが多くの研究で示されています。
さらに注意したいのが睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。眠っている間に呼吸が止まる病気で、本人は『いびきが大きい』程度にしか思っていないことが多いですが、夜間に低酸素状態が繰り返され、心臓や血管に大きな負担をかけています。その結果日中の強い眠気、集中力の低下、生活習慣病の悪化につながるのです。SASは睡眠ポリグラフ検査(PSG)で診断されます。まずは、問診→自宅にて簡易検査→必要であれば医療機関に一泊して検査となります。思い当たる方は一度検査を受けられることをおすすめします。
まとめ
ここまで『睡眠の役割』や『質を高めるための工夫』をお伝えしてきましたが、大切なのは完璧を目指さないことです。柳沢先生が提唱するように、まずは『減点法』でマイナス要因を減らすことから始めましょう。
・寝室を少し暗くしてみる
・寝る前のスマホをやめてみる
・寝酒を控えてみる
・眠くなってから布団に入る
今日からでも取り入れてみてください。また、『自分に合った睡眠』を見つけることも大切です。睡眠時間は人によって6時間で足りる方もいれば、8時間必要な方もいます。大事なのは『日中に眠気や集中力の低下がないか』を基準に、自分にとってのベストを探ることです。睡眠は、体力を充電し、脳をアップデートするための欠かせない時間です。睡眠不足が血圧や血糖、ホルモンバランスに与える影響を実感しています。そして睡眠時無呼吸症候群のように気づかないうちに体に負担をかけている病気も少なくありません。だからこそ、『睡眠時間を削ることは、未来の健康を削ること』と意識することが必要です。今日からできる小さな工夫で、あなたの睡眠の質は大きく変わります。ぜひ、ご自身にあった習慣を少しずつ取り入れて、心と体のリズムを整えてみてください。
最後までお読みくださりありがとうございます