前回の記事では、『片付けられないのは性格の問題ではなく、脳の癖によるもの』というお話をしました。多くの人が『やる気が出ない』『気づいたら散らかっている』と感じるのは意志の弱さではなく、脳が情報を処理する仕組みに違いがあるからです。とはいえ、頭では理解しても『じゃどうすれば上手く片付けられるの?』というところが一番気になりますよね。実はここからが、片付けがうまくいくかどうかの分かれ道。なぜなら、片付けのつまずき方は人によって違い脳のタイプによって対処法も変わるからです。
たとえば、情報が多すぎて考えがまとまらない人。感情が先に動いて、手が止まってしまう人。完璧を目指しすぎて動けなくなる人。どれも『片付けたい気持ちはあるのに、うまく進まない』という共通点がありますが、原因も解決策もそれぞれ違います。ここで大切なのは、『できない自分を責めること』ではなく、『自分の脳がどう動くのか』を知ること。自分のタイプを理解すれば、無理に頑張らなくても自然に片付けが続くようになります。今回は、そんな”片付けられない脳”を4つのタイプに分けて、それぞれの特徴と解決策をわかりやすく紹介します。あなたの”片付けが進まない理由”がきっと見つかるはずです。
片付けがうまくいかないのは”脳の仕組み”の違い
私たちはつい、『片付けられない=だらしない』『やる気がない』と自分を責めてしまいがちです。けれど実際は、脳の働き方や情報処理のクセによって、片付けの得意・不得意が大きく変わります。たとえば、同じ『散らかった部屋』を見ても、すぐに全体を把握して手を動かせる人もいれば、情報が多すぎてどこから手をつければいいのかわからなくなる人もいます。これは『脳のワーキングメモリ(短期的に情報を保持しながら作業する力)』や『報酬系(達成感を感じる仕組み)』の違いによるもの。つまり脳のタイプが違えば、片付けのやり方も変える必要があるのです。
片付けがうまくいかないのは、意志が弱いからでも、性格のせいでもありません。『自分の脳がどんなパターンで動いているのか』を知ることが、解決の第一歩です。次では、4つのタイプ別に『片付けられない脳のクセ』と『うまく付き合うためのコツ』を紹介します。自分に当てはまるものを見つけて、無理のない片付け方を見つけていきましょう。
タイプ①:情報過多タイプ—— 考えすぎて動けないあなたへ
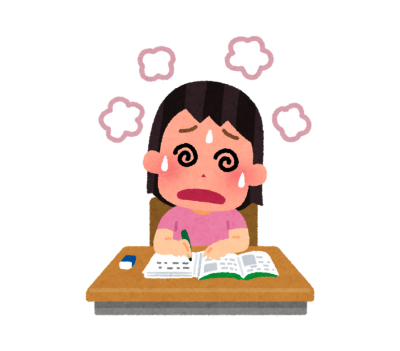
このタイプは、とにかく情報を集めすぎて頭の中がいっぱいになってしまう傾向があります。『これも使えそう』『SNSで見た収納法が良さそう』と常に新しい情報をキャッチ。『断捨離』『ミニマリスト』『ライフオーガナイズ』・・情報が溢れすぎていて何から始めていいのかわからなくなる。あれもこれもと考えているうちに、どれを選べばいいのか分からなくなってしまう。結果片付けが始められない・・そんなループに陥りやすいのです。
情報過多タイプの人は、脳の”ワーキングメモリ(短期記憶の作業スペース)”が情報でいっぱいになりやすい傾向があります。あれもこれもと同時に考えるうちに、脳がオーバーヒートして『選べない』『動けない』状態になってしまうのです。つまり情報をたくさん持っているのに、処理が追いつかない状態。片付けという”実行”よりも、”思考”でエネルギーを使い果たしてしまっています。
また、情報を集めすぎる背景には『失敗したくない』という完璧主義な思考も隠れています。『せっかく片付けるなら、正しい方法で』『後で後悔したくない』と考えるほど、選択肢が増えて判断が難しくなる・・。これがまさに”選択のパラドックス”です。情報が多いほど自由になれるように見えて、実際には脳が混乱してストレスを感じやすくなります。
このタイプの解決策は、『情報を減らす勇気』を持つこと。たとえば、この人の方法を3ヶ月だけ真似してみよう』『雑誌やSNSを見るのは片付け後にする』など、意識的に”絞る”だけで驚くほど動きやすくなります。脳は、『やることが明確な時』に最も集中力を発揮するため、情報を減らすことが最大の効率化につながるのです。もう一つ大切なのは、『情報を集める自分を責めない』こと。情報過多タイプの人は、探究心があり、物事を丁寧に理解したいという強みを持っています。その力を『自分に合う方法を選ぶ力』へと切り替えれば、片付けはぐっとスムーズになります。
解決策
まず『今の生活に必要な情報だけ』に絞る
収納法や片付け本は、1冊だけに決めてやってみる
モノを見ながら考えず、『今日はここだけ』と範囲を限定する
情報は減らすほど脳がスッキリして行動しやすくなります。”選ぶ力”を取り戻すことが、片付け再スタートの第一歩です。
タイプ②:感情優先タイプ——モノへの想いが強く、手が止まってしまうあなたへ

『これ、子供が小さい頃によく使ってたな・・』『これは思い出があるから』『高かったからもったいない』そう感じて手放せないのがこのタイプ。感情が先に動くため、理屈ではわかっていても、心が追いつかないのです。実は感情優先タイプの脳は”情動系(扁桃体)”がとても活発です。モノを見ると、その時の感情や体験が一瞬で呼び起こされるため、『ただのモノ』として判断できにくいのです。
また、『楽しかった』『嬉しかった』といったポジティブな記憶だけでなく、『捨てたら後悔するかも』『もったいない』という不安も同時に強く働きます。そのため脳が”危険回避”モードに入り、手放す決断ができなくなってしまうのです。
一方で、感情優先タイプの人は『空間の心地よさ』にも敏感です。だからこそ、片付けを”感情に寄り添う作業”として捉え直すと、スムーズに進むことがあります。たとえば、『どのものが今の自分を心地良くしてくれるか』という視点で選ぶ。『過去』ではなく『これからの自分』が喜ぶかどうかを基準にすると、感情の整理も自然と進みます。
また、『気分が乗らないと動けない』という特徴もこのタイプに多くみられます。無理にやる気を出そうとするより、『気分が上がる音楽を流す』『朝の光が入る時間に取り組む』など、感情を味方にする環境づくりがポイントです。自分の心のリズムを知ることがこのタイプの片付けへの近道です。
感情優先タイプは、決して『片付けが苦手』なのではなく、『モノや記憶を丁寧に扱える繊細な感性の持ち主』です。その感性を『今の幸せ』を選び取る方向へ使えば、片付けはきっと楽しい時間に変わります。
解決策
過去ではなく『これから使うか』で判断する
手放す前に写真を撮って、記憶の中に残す
”ありがとう”を言葉にして区切りをつける
感情を否定せず、優しく区切りをつけること。思い出を大切にしながらも、今の自分を軽くしていく片付け方が合っています。
タイプ③:行動後回しタイプ——『あとでやる』が口ぐせのあなたへ

『片付けなきゃ』と思いながらも、つい後回しにしてしまうタイプ。『今日は疲れたから明日』『週末にまとめてやろう』と思っているうちにどんどん先送りになってしまいます。このタイプの脳は、タスクを『先のこと』として処理する傾向が強く、”今すぐやる”ためのエレルギーを起こしづらいという特徴があります。また、脳は”先が見えないこと”に不安を感じる性質があります。片付けのようにゴールが曖昧な作業は、『どこまでやれば終わるのか』がわかりにくいため、脳が行動をためらうのです。
さらに『完璧にやらなきゃ』という意識が少しでもあると、脳の負担が増してますます動けなくなる・・。つまり、”やる気がない”のではなく、”脳が行動をストップさせている”のです。対処法としては、『始めるハードルを下げる』ことが何より効果的。たとえば、『10分だけ片付ける』『机の上だけやる』など、”小さな行動”に分ける。脳は一旦行動を始めると”作業興奮”と呼ばれる状態になり、やる気が後からついてくる仕組みになっています。
また、『やらなきゃ』を『やってみよう』に言い換えるのもおすすめです。脳は”命令形”より”提案形”の方がストレスを感じにくく、前向きに動きやすいからです。行動後回しタイプに必要なのは、厳しさではなく、工夫と優しさ。『小さく始めて、続けられた自分を認める』・・この積み重ねこそが、無理のない片付け習慣をつくる第一歩です。
解決策
作業を15分以内で終わるサイズに分ける
”片付けのスタートスイッチ”を決めておく(音楽やアロマ、タイマーなど)
やった後の気持ちを想像してから動く
脳は”やり始める”と自然にやる気が上がる仕組みになっています。まずは少しの時間でいいので、動き出すことが何よりの特効薬です。
タイプ④:完璧主義タイプ——理想が高くて動けない、がんばり屋さんのあなたへ

このタイプは『どうせやるなら完璧に片付けたい』『中途半端にしたくない』と思うあまり、最初の一歩が踏み出せません。『時間ができたら』『ちゃんと整理できるときに』と考えているうちに、結局手がつかないままになってしまう。実はこのタイプ、脳の『報酬系』と『前頭前野』が関係しています。完璧を目指す人ほど、ゴールまでの道のりを細かく想像してしまうため、脳が”疲労感”を先に感じてしまうのです。『全部綺麗にしなきゃ』『どうせなら収納も見直したい』と思った瞬間、脳は膨大なエネルギーを必要と判断し、結果として行動が止まります。
また、完璧主義タイプは『片付け=終わらせるモノ』と捉えがち。でも実際は、片付けは”暮らしを整えるプロセス”です。つまり『完成させる』ではなく、『整えることを続ける』意識の方が現実的。
『完璧を目指さない=手抜き』ではなく、『現実の自分を尊重する片付け方』に変えるということ。『ここまですれば気持ちいい』『この状態で十分動きやすい』と感じるラインを見つけることが、このタイプの片付け成功のカギになります。”70点でOK”なのです。
解決策
完璧ではなく”ちょっとマシ”を目指す
『使いやすい』『取り出しやすい』など、目的をシンプルにする
15分だけ、1か所だけなど、小さな成功体験を重ねる
タイプ⑤:収集家タイプ——”持つこと”で安心する、コレクター気質のあなたへ
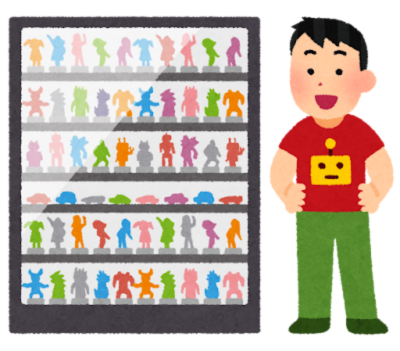
気づけば似たような洋服や食器、雑誌がたくさんある。旅行先で買ったお土産や、限定グッズが手放せない。『見ると楽しい』『持っているだけで安心する』・・そんなあなたは”収集家タイプの傾向があるかもしれません。このタイプの人の脳は、報酬系(ドーパミン系)の働きが強く、『手に入れる』ことに快感を覚えやすい特徴があります。新しいものを見つけたり、集めたりすることで脳が”小さな達成感”を感じるのです。いわば、『集めること』そのものが喜びであり、ストレス解消や自己表現の一部になっています。
しかし、その一方で、ものが増えるほど『整理しよう』『減らさなきゃ』という意識が芽生え、矛盾したストレスを抱えやすくなります。脳の報酬系が”手に入れる快感”を求めるのに対し、”片付けて減らす行動”はドーパミンの報酬を得にくいからです。つまり、脳にとって”捨てる”は報酬がない行為。だから、手放すことを後回しにしてしまうのです。
このタイプへのアプローチは、”減らす”ではなく”選び抜く”こと。『全部とっておく』ではなく、『本当にお気に入りを残す』という方向に意識を変えると、脳が『好きなものに囲まれている』という新しい報酬を得られます。また、『見えない場所に収納』より『見える形で飾る』方が、心理的な満足度が高まりやすく、所有感を保ちながらモノを減らすことができます。
収集家タイプは、本来『価値を見抜く力』『好奇心の強さ』を持つ人です。それは、片付けを通して”今の自分が大切にしたい価値観”を選び直すチャンスにもなります。集めてきたモノはあなたの歩んできた証。だからこそ、これからは、『自分を心地よくしてくれるもの』を中心に集めていけばいいのです。
職場ではできるのに、家庭では片付けられない理由

職場では整理整頓がきちんとできるのに、家庭ではなぜかうまくいかない・・。そんなふうに感じたことはありませんか?実は私自身、臨床検査技師として働く中で、まさにそのギャップをなん度も実感してきました。検査室の中では、どの試薬がどこにあるのか、どんな順序で作業するのか、全てが明確に決まっています。”迷わない仕組み”が整っているからこそ、判断の回数が少なく、効率的に動けるのです。ところが、家庭では使う人も目的も日によって違い、自分で判断しなければならない場面ばかり。『捨てる』『残す』『しまう』『とりあえず置く』・・その度に脳は判断を繰り返しています。
人間の脳は、1日にできる判断の回数に限界があると言われています。朝から仕事・家事・人間関係で数え切れないほどの選択をしている私たちは、夜になるともう”決断疲れ”を起こしているのです。そんな状態で片付けに向かおうとしても、脳が『もう考えたくない』とブレーキをかけてしまう。だからこそ、片付けを後回しにしてしまうのは当然の反応なのです。
職場では”ルールが決まっている”から迷わない。家庭では”ルールを自分で作らなければならない”から迷う。つまり、家庭の片付けには『自分の脳が判断しやすい仕組み』を作ることがカギになります。
たとえば、
・よく使うモノは『すぐ手に取れる位置』に置く
・迷うものは『保留ボックス』を決めておく
・『とりあえず置く場所』を限定する
こうした小さなルールを決めておくだけで、判断の回数が減り、脳がぐっと楽になります。片付けが続かないのは、やる気が足りないからではなく、脳が疲れているから。その仕組みを理解すれば、『できない自分』を責める必要はありません。家庭の中にも、職場のように”判断しなくても動ける仕組み”をつくること。それが、無理なく片付けが続く第一歩です。
まとめ
片付けがうまくいかないのは、性格がだらしないからでも、意志が弱いからでもありません。多くの場合、それは『脳のくせ』や『思考の傾向』によるもの。情報過多タイプは決断に疲れ、感情優先タイプは思い出と向き合い、行動後回しタイプはエレルギーを溜め込み、完璧主義タイプは理想の高さに足を止める・・。収集家タイプもまた、『持つことで安心』を得ているのです。私たちは誰もが、これらの要素を少しずつ持っています。日によって違うタイプが顔を出すこともあります。だからこそ、片付けに『正解』や『完璧な方法』はありません。自分の脳の傾向を知り、『ああ、私はこういうタイプだから』と気づくだけで、心のハードルはぐっと下がります。
職場では『誰が使ってもすぐわかる』ように整理整頓されており、効率を最優先にした配置が徹底されています。でも、家庭はそうはいきません。そこには、『感情』『思い出』『自分らしさ』が入り込むから。だからこそ、家の片付けは『管理』ではなく『選択』。モノを通して、自分にとって何が心地よいのかを知る作業なのです。片付けは、脳と心を整えるトレーニングでもあります。自分を受け入れ、小さな一歩から始めることで、暮らしにも心にも余白が生まれます。そしてその余白が、『これからの自分』を描くためのスペースになるのです。
最後までお読みくださりありがとうございます
\あわせて読みたい/

