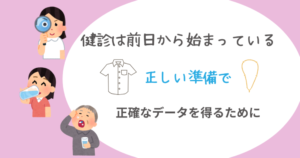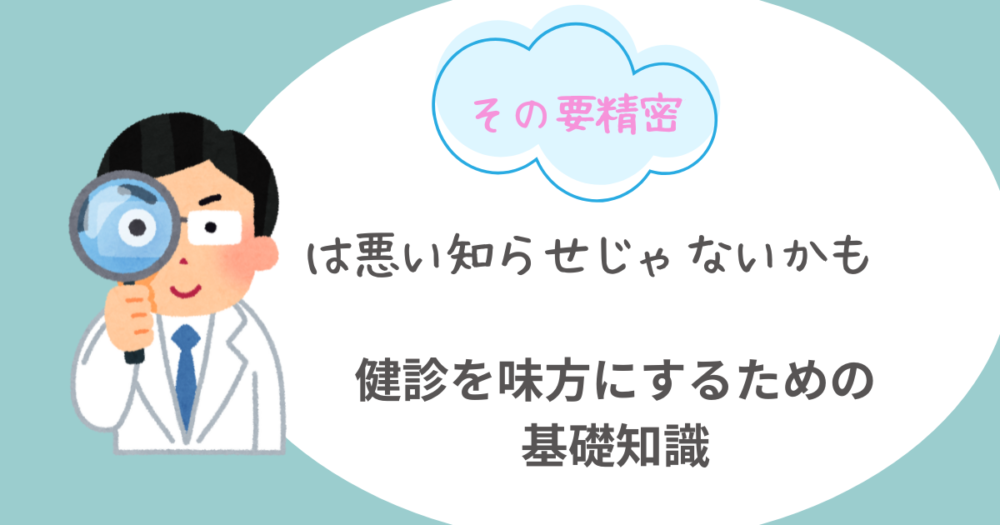毎年の健康診断。封筒を開ける手が少し止まる・・そんな経験、ありませんか?『また引っかかってるかも』『何か悪いのかな』と不安になるあの瞬間。けれど実は、”要精密”という判定は、”悪い結果”というよりも、”もう少し詳しくみてみましょう”ということがほとんどです。健診では少しでも疑わしい場合、安全を優先して精密検査を勧める仕組みになっています。つまり”引っかける前提”で運用されているとも言えるのです。むしろ、この段階で見つけられることが健診の目的でもあるのです。今回は、『健診と検診の違い』『なぜ判定が違うのか』、そして『結果をどう活かせばいいのか』を、臨床検査技師の視点も交えながらわかりやすくお話しします。
『健診』と『検診』は、似ているようで全く違う
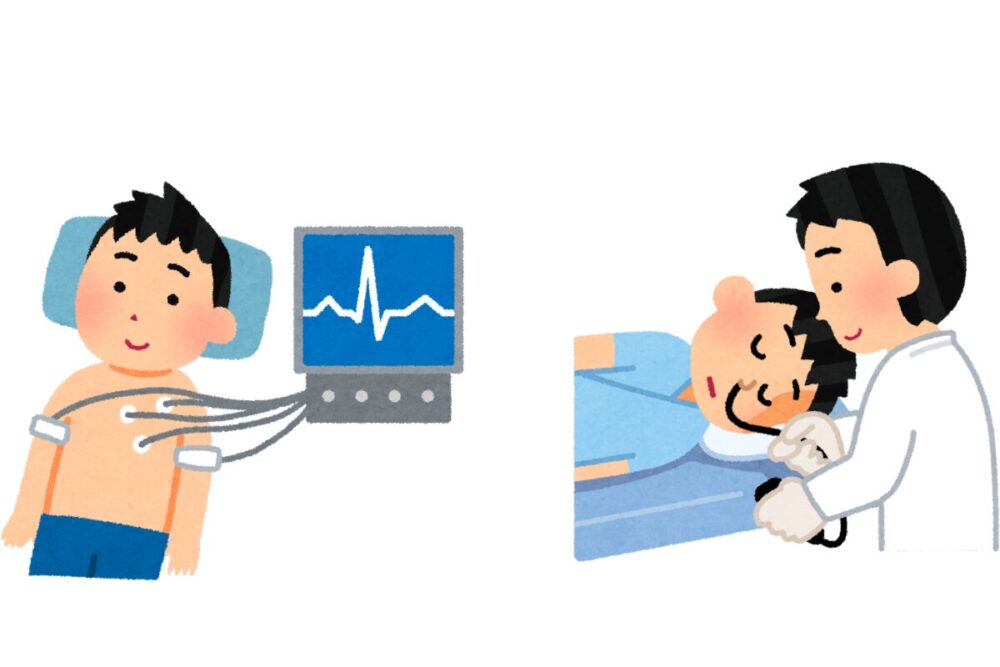
『健康診断(健診)』と『がん検診(検診)』。名前が似ているため、同じようなものだと思われがちですが、目的も内容も全く違います。
まず、健康診断(健診)は、生活習慣病を中心に、体全体の健康状態を確認するもの。職場や自治体で行われる定期検診はこのタイプで、血圧・血液・心電図・胸部X線などを通して、日常の生活習慣による変化を早めに見つけるのが目的です。
一方でがん検診(検診)は特定の病気・・たとえば乳がん、大腸がん、子宮頸がんなど・・を早期発見するための検査。つまり健診が『今の健康を確認する』のに対し、検診は『まだ症状のない病気を探す』ために行われます。
実際、職場健診の項目だけでは”がんの早期発見”には限界があります。たとえば、女性に多い乳がんや子宮頸がんは、別途の検診でしか見つけられません。だからこそ、健診を『全身の健康チェック』、検診を『ピンポイントで病気を探す検査として、両方をうまく組み合わせることが大切です。
もう一つ大事なのは、『目的の違い』を理解すること。健診は”ふるいにかけてリスクを拾い上げる”のが役割。一方病院の検査は”診断を確定させる”のが目的です。『健診で引っかかったけど、病院では何もなかった・・』これは間違いではなく、今の健診の役割としてはよく起こることです。異常を疑って早めに医師につなぐことで、大きな病気を未然に防いでいるのです。
健診と病院、同じ”検査”でもみているものが違う
『検診で引っかかったのに、病院では”異常なし”と言われた』・・そんな経験はありませんか?少しもやっとするこの現象、実は精度の”ズレ”ではなく、目的の違いから生まれるものです。
健診は『リスクを拾い上げる』ためのもの
健診の役割は、まだ症状のない人の中から『将来、病気になる可能性のある人』を早期に見つけることです。そのため、判定基準は”厳しめ”に設定されています。たとえば、『血圧や血糖値なども少し高めかな?』という段階で”要経過観察”や”要精密”となります。これは”病気の診断”ではなく、”将来的な変化のサインを見逃さない”ための判断。いわば大きめの網でリスクをすくい取るようなイメージです。
病院は『確定診断』をつける場所
一方、病院では『現時点で治療が必要かどうか』を見極めるのが目的です。つまり、健診の”要精密”を受けて来院した場合でも、医師はより詳しい検査を行い、医学的に”異常あり”と診断できなければ『問題なし』と伝えることになります。両者は対立するものではなく、連携して私たちの健康を守る仕組みなのです。
“異常なし”にも意味がある
精密検査の結果、問題がなかったとき、『健診の結果はまちがいだったの?』と感じる人もいるかも知れません。でも、そうではありません。健診で引っかかったということは、体の変化のサインを出していたということ。病気ではなくても、『生活習慣を見直すきっかけ』として受け止めることが大切です。次回の健診で数値が安定していれば、それは立派な成果です。
かかりつけ医の存在がカギになる
健診と病院の間を繋いでくれるのが、『かかりつけ医』です。毎年の健診結果を把握してくれる医師がいれば、『去年より血糖値が上がっている』『肝機能が少しずつ変化している』といった経年変化を正しく読み取ってもらえます。
病気の早期発見もこうした”比較データ”の積み重ねから始まります。一度きりの数値ではなく、”自分の変化の傾向”を共有できる信頼できる医師を持つこと。これが、これからの時代の健康管理には欠かせません。
未来への第一歩:マイナ保険証でつながる医療と健診

今後、マイナ保険証の導入によって、健診データと医療機関の情報が連携できる仕組みが進んでいきます。これが実現すれば、同じ検査を何度も繰り返す必要が減り、”健診と医療のちがい”を超えて、一人ひとりの健康情報をトータルで管理できる未来が見えてきます。医療費の無駄も抑えられ、かかりつけ医にトータルで管理してもらえる未来が待っています。健診と病院のそれぞれの目的を知って上手に使い分けることが、安心して歳を重ねるための第一歩です。
がんを”早く見つける”という選択〜男女別に見る検査のポイント〜
健診でみる数値も大切ですが、もう一つ忘れてはいけないのが『がん検診』。生活習慣病のように”数値の変化”で予兆が掴める病気もあれば、がんのように自覚症状が出にくいまま進行する病気もあります。だからこそ、定期的ながん検診が『未来の安心』につながります。
がん死亡率順位(2023年)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 女性 | 大腸がん | 肺がん | 膵臓がん | 乳がん | 胃がん |
| 男性 | 肺がん | 大腸がん | 胃がん | 膵臓がん | 肝臓がん |
有効な検査:
大腸がん→便潜血検査→大腸内視鏡検査
肺がん→胸部X線→胸部CT
膵臓がん→(腹部エコー検査)→(造影CT)→*MRCP
乳がん→マンモグラフィ+超音波(エコー)検査
胃がん→胃内視鏡検査(胃カメラ)
子宮がん→子宮頸部細胞診や**経膣超音波検査
がん検診とひとことで言っても、検査にはそれぞれ”得意・不得意”があります。どんなに精度の高い検査でも『絶対に見逃さない』わけではなく、逆にリスクや負担が伴う検査もあります。大切なのはどんな特徴があるのか知った上で選ぶことです。
*MRCP検査とは、MRI装置を使って胆のう・胆管・膵臓を同時に調べる画像検査です。体にほとんど負担をかけずに胆のうや胆管がん、膵臓がんの早期発見などに役立つ検査です。
**経膣超音波検査とは、膣内に超音波プローブを挿入し、子宮内膜の厚さや構造の異常を画像で確認します。エコー検査なので、放射線被ばくの心配はありません。
大腸がん
便潜血検査は、血液が混じっているかをみる簡易検査です。負担が少なく有効な方法ですが、確実な検査とは言えません。血縁関係のある家族に大腸がんの方がいる、または便潜血検査で陽性になった場合は、大腸内視鏡検査を検討すると安心です。
胃がん
胃がんの検査には『バリウム検査』と『胃内視鏡検査』があります。バリウム検査は全体像を掴むのに役立ちますが、検査後に引っかかると結局胃カメラを受けるケースも多いのが実情。放射線被ばくや便秘などのリスクもあるため、できれば最初から胃内視鏡(胃カメラ)を選ぶ方が効率的です。
乳がん
乳がん検診では、マンモグラフィと超音波(エコー)検査の両方を組み合わせるのがおすすめ。特に乳腺が発達しているとマンモグラフィだけでは不十分なことが多い。年齢や乳腺の状態に合わせて、医師と相談しながら2つの検査を併用するのが安心です。マンモグラフィが痛くてどうしても受けたくない方は、乳腺エコーだけでもいいので受けるようにしましょう。そして検診のマンモグラフィで引っかかったら、乳腺外科を受診することをおすすめします。
年齢とともに変わる”数値のゆらぎ”
40代までは基準値内だったのに、50代に入ってから少しずつ上がる血圧やコレステロール。これもホルモンバランスや代謝の変化による”年齢のサイン”です。特に女性は更年期を境に脂質代謝が変わり、LDLコレステロールが上がりやすくなります。また、筋肉量が減ることで血糖値のコントロールも難しくなります。大切なのは”悪化”と”変化”を区別すること。1回の結果で一喜一憂せず、過去3年分くらいを並べて『流れ』でみると、自分の体の特徴がつかめます。数値は、体の”声”のようなもの。上がった・下がったの背景には、生活やストレス、睡眠の影響も潜んでいます。
かかりつけ医を持つことの大切さ
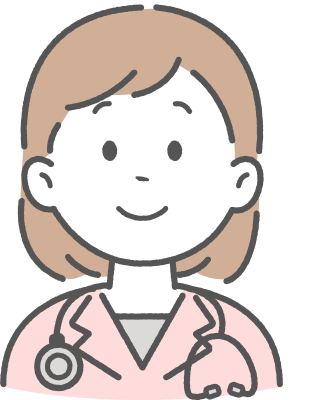
健康診断の結果一つひとつは大切な検査です。でも、『数値』そのものよりも、その結果をどう生かすかという視点です。健診の結果は”ゴール”ではなく”スタート”です。異常値が出てもすぐに不安になる必要はありません。再検査や経過観察が必要なのか、それとも生活改善で様子を見るのか・・判断のかカギを握るのがかかりつけ医の存在です。
検査結果を手にしたとき、多くの人は『これって大丈夫?』『どこにいけばいいの?』と迷います。そんな時に、気軽に相談できる医師がいるかどうかでその後の行動が大きく変わります。かかりつけの医師は、あなたの体の”変化の記録”を長期的に見てくれる存在。単発の数値だけでなく、これまでの推移や生活背景を踏まえて判断してくれるため、無駄な心配や不要な検査を避けることができます。
また、何かあったときに『この先生に相談すれば大丈夫』という安心感は精神的な支えにもなります。特に50代以降は、体調の変化がゆるやかに、しかし確実に現れる時期。長く信頼できる医師を持っておくことは自分の未来への”お守り”のようなものです。もし今、特定のかかりつけ医がいない場合は、健康診断の結果をきっかけに探してみてください。診療スタイルや話しやすさなど、自分と相性の良い先生を見つけることが大切です。病院の規模よりも、『この人なら相談できる』と思える信頼感が第一です。
健診結果を”読み解く”ことは、数字をみるだけではなく、自分の体と向き合い、今後の暮らしをより良くする第一歩。『検査で終わり』ではなく、『検査から始まる』・・そんな視点で、次のスッテップへ繋げていきましょう。
健診のこれから〜マイナ保険証が繋ぐ医療の未来
私たちの健康管理のあり方は、今大きな転換期を迎えています。それを象徴するのが、『マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)』です。これまで健診結果は紙で渡され、病院ごとに記録がバラバラに管理されていました。しかし、マイナ保険証の普及により、医療機関や薬局、健診センターが一人ひとり医療情報を共有できる時代へと移りつつあります。
たとえば、健診で血糖値の上昇を指摘され、その後別のクリニックで再検査を受けた場合。従来なら健診と病院のデータは切り離されており、同じ検査を再び受けることも珍しくありません。しかし、今後はマイナ保険証を通して過去の健診データや服薬情報、既往歴が自動的に共有され、医師がより正確にあなたの状態を把握できるようになります。
これまで、健診や初診のたびに『今までかかった病気』『服薬中の薬』などを紙に書いたりするのが当たり前でした。けれども、マイナ保険証の仕組みが整えば、これらの情報は電子的に確認できるため、医療現場では”確認作業”に留まり、無駄な質問や書類記入が減るようになります。
それはつまり、検診の受付や問診がスムーズになり、受診時のストレスがぐっと減るということ。『何度も同じことを聞かれる』『毎回書くのが面倒』という小さな負担がなくなれば、健診をもっと気軽に受けられるようになるでしょう。これは、忙しい現役世代にとっても大きなメリットです。
マイナ保険証を使えば、健診データが電子的に記録され、医師だけでなく本人もオンラインで閲覧・管理できるようになります。体重や血圧、血糖値などの推移をグラフで確認すれば、『去年より改善している』『少し気をつけた方がいい』など、自分の体と対話する感覚が得られます。また急な体調変化が起きた時でも、過去の検査結果や服薬情報が医療機関で瞬時に参照できるため、診断や治療がよりスムーズに進みます。つまり、マイナ保険証は自分の代わりに体の履歴書を語ってくれる存在になるのです。
こうして、健診は『1年に1度の点検』から、『生涯を通じた健康のパートナー』へと変わりつつあります。情報がつながることで、医師と患者が同じデータを見ながら話せる関係になり、より主体的に自分の健康をマネジメントできるようになります。健診の目的は、病気を見つけることだけではありません。自分の体を知り、これからの暮らしをより良くしていくための”地図”を描くこと。マイナ保険証がつなぐ新しい医療のかたちです。
まとめ
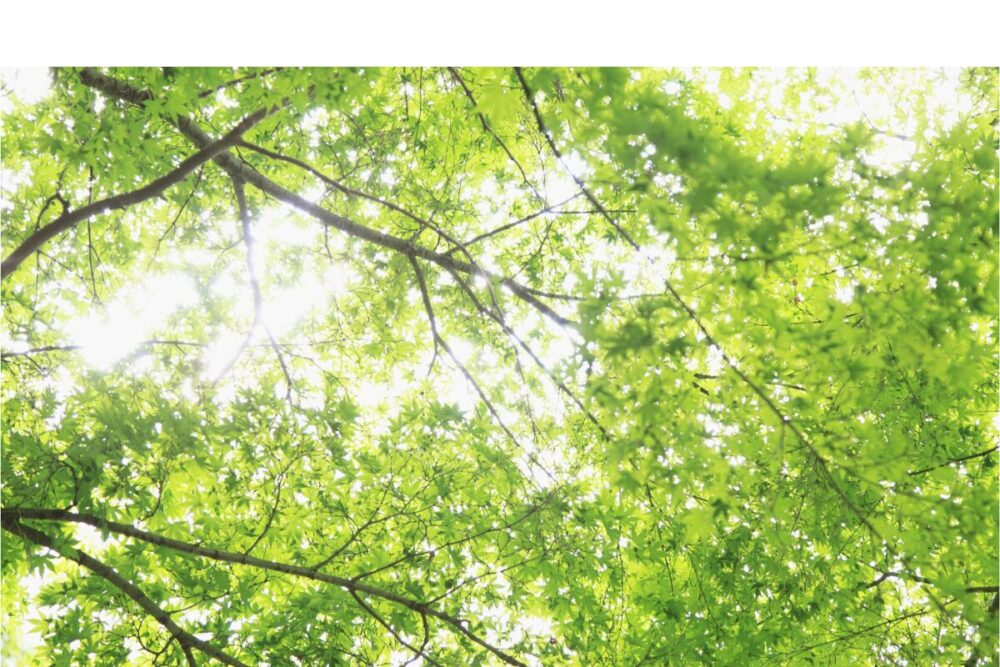
健診やがん検診を受けることは、決して『怖いこと』ではありません。それは、これからも自分らしく生きるために”体と向き合う時間”です。40代、50代は、仕事や家族、親の介護など日々を頑張るあまり、自分の体を後回しにしがちな年代。けれどもこの時期こそがんや生活習慣病のサインを早く見つけられるラストチャンスでもあります。がんは早期発見であれば治療の選択肢が多く、治療後の生活の質(QOL)も上がりやすい。生活習慣病も同じで、少しの意識と行動でコントロールできることが多いのです。早い段階であれば、薬に頼らず食事の工夫で”美味しく食べながら健康を守る”ことも十分にできる時代です。適度に体を動かし、よく眠り、心地よいリズムを取り戻す。それが、人生後半戦をもっと楽しむための”体づくり”です。
さらに、マイナ保険証によって、”自分の健康情報を自分で活かせる”未来が、すぐそこまで来ています。だからこそ今のうちに『かかりつけ医』を持ちましょう。何かあった時に相談できる場所があることは、心の支えにもなります。健診で気になる結果が出ても、そこからどう向き合うかを一緒に考えてくれる存在がいれば、”病気を防ぐ医療”がようやく本当の意味で形になっていきます。生活習慣病を上手にコントロールすれば、美味しく食べて、好きなことに打ち込み、旅や趣味も思いっきり楽しめる・・そんな未来が私たちの目の前に広がっています。未来の安心はある日突然やってくるのではありません。今日、健診・がん検診を受けようと決めたその一歩が、”自分の未来を明るく変えるはじまり”になるのです。
最後までお読みくださりありがとうございました